レザーケア商品の成分について
レザーケア商品には「オイル」「クリーム」「ローション」など革の状態に合わせて様々なケア商品があります。
それぞれの違いとしては、革の性質に合わせてだったり、ケッペン気候区分で分けられるようにその地域の環境だったりに合わせた革のケアを行う必要があるため様々なケア商品を作らなければカビてしまったり、硬くなり割れてしまったりと品質を保つことができなくなってしまうためです。
今回の記事は、ケア商品に様々な成分が使用されているのですが、例えば有名なところでは、ミンクオイル、ホホバオイルやシダーウッドオイル、ほかにもビーズワックス(蜜蝋)だったり、ラノリン、ワセリン、有機溶剤など、そういった成分がどういった作用を持っているのか、革にとってどういった効果・効能があのか自分が疑問に思ったレザーケアの成分について、様々な見解をもとに個人的にまとめてみましたので、ご紹介したいと思います。
注意:個人的見解であり、実際の作用とは異なる可能性があります。
基剤
まず初めにご紹介するのは、クリーム性のケア商品の基となる基剤についてご紹介します。
ワセリン
ワセリン(Petroleum)は、石油から得た石油系飽和炭化水素の混合物を脱色して精製したもので作られています。ただし不純物を取り除いてはありません。不純物を取り除いたものは医療用として扱われている「プロペト」という商品名で販売されています。
Vaseline(ワセリン)はユニリーバの商標ですが、世界では一般名詞となっています。
組成
ワセリンは固形炭化水素の中に液状炭化水素が乳化したコロイド状態であると考えられています。
パラフィン(石蝋/せきろう)
パラフィン(paraffin)は、炭化水素化合物(有機化合物)の一種で、炭素原子の数が20以上のアルカン(鎖式飽和炭化水素である。メタン系炭化水素、パラフィン系炭化水素や脂肪族化合物)の総称。
語源はラテン語のParum affinisで親和性が低いという意味です。
固形のものはロウソクやクレヨンに利用されています。
流動パラフィン
身近なものでは、クレンジングオイル、ベビーオイル、ハーバリウム用オイルなどボディケア商品や食品製造過程での利用、機械オイルに利用されている。常温では無色の液体で非揮発性。水には不溶。化学的に安定な物質で、通常の条件では酸化を受けない。成分については固形のパラフィンよりオレフィン系炭化水素に富む。乳化しやすく伸びや浸透性に優れる。純度は紫外光の吸光度により計測される。
流動パラフィンの商品名、呼び名
ヌジョール (nujol)、ホワイト油、白色鉱油、水パラフィン、ミネラルオイル、ミネラルオイルホワイト、医療用パラフィン (medicinal paraffin)、パラフィンワックス、saxol、USP mineral oil、adepsine oil、Albolene、glymolなど。
動物性蝋(どうぶつせいロウ)
ラノリン
ラノリンは、ウシ科動物ヒツジ(学名:Ovis aries 英名:Sheep)の皮脂分泌物(羊毛脂/ウールグリース:wool grease)を精製して得られる動物性ロウです。名前は、ラテン語でwoolを意味するLannaにちなんでラノリン(lanolin)と命名されました。
特徴としては、ウールグリースは羊毛を柔軟かつ強靭に保つ役割をしており、これは人間の皮膚上における皮脂膜に似た機能であり、また約2倍の量の水を吸収する抱水性があります。
ラノリンの組成
アルコール(75種類)と脂肪酸(138種類)で構成されています。
抱水性エモリエント作用
ラノリンには「抱水性エモリエント作用」と言いう特性があります。ラノリンは人の皮脂膜と似た組成をしていることから、皮膚との親和性が高く、また軟性にも優れているため皮膚への高い浸透性を持っています。抱水性に関しては、抱水性が高い油剤はエモリエント効果(肌が水分をたっぷり含んで潤い柔らかくなりやすい作用)が高いことが知られていますが、ラノリンは古くから高い抱水性が知られており、この抱水性はラノリンがもつ多様なステロールエステルの高次構造の中に水分が分散して保持されることによるものです。
光沢付与性
ラノリンは高い屈折率(1.475)ちなみにエタノールが1.3618、水晶が1.5443、ダイヤモンドが2.417です。光沢を付与するの付与目的で使用されています。
アレルギー
ラノリンによりアレルギー反応が生じることは確実だといわれており、ラノリンのアレルギー原因物質が、ラノリンの75種類あるアルコールの成分および一部の遊離アルコールであることが分かっています。皮膚に付着した場合アレルギー症状が出現する場合があります。症状が出たら早急に医師へ相談しましょう。
ビーズワックス(蜜蝋/ミツロウ)
ビーズワックス(bee’s wax)は、ミツバチ課動物ミツバチ(学名:Apis mellifera 英名:Honey bee)の巣の製造工程で生成されます。ミツバチは花の蜜を集めるのは有名ですが、働きバチは採蜜できる量が多いと、蜂蜜の貯蔵庫が満杯になるため、体内に蜜を貯め込み一部が体内で蜜蝋に変換されます。変換された蜜蝋は腹の裏面の蝋腺から分泌し、すぐに硬化(硬化したものを蝋板という)してしまうため、
それを別の働きバチが口でかみ砕き、蜂の巣(ハニカム、honeycomb)を構築する材料に使われます。
蜜蝋の採取の仕方としては、巣を取り出してスライスし、温めることで蜜蝋が溶解し、その蜜蝋をろ過して蜂蜜、さらに巣を遠心分離して蜂蜜を採った後、巣を水洗し、鍋で煮込んで冷やし固めることで蜜蝋を作ります。
蜜蝋は、製造工程で2種類に分けられ精製・漂白前のミツロウを黄ロウ、精製・漂白したミツロウを白ロウまたはサラシミツロウと呼びます。
化粧品成分表示名では、サラシミツロウであってもすべて「ミツロウ」と記載されます。
ビーズワックスの組成
モノエステル(約35%)、炭化水素(約14%)、ジエステル(約14%)、遊離酸(約12%)、ヒドロキシモノエステル(約8%)で構成されています。成分の多くは精製の過程で副産物として作られている可能性があります。また巣を作ったミツバチの種類によっても成分の比率に違いが生じます。
粘稠性、可撓性、可塑性
ミツロウはロウ類の中でもとくに粘稠性があり、さらに可撓性(粘り気があること)、可塑性(外力が加わることでしなやかにたわむ性質)を付与する目的で他の油性成分と組み合わせて使用されます。
植物性蝋(しょくぶつせいロウ)
カルナバワックス(カルナウバロウ)
ヤシ科植物カルナウバヤシ(学名:Copernicia Cerifera 英名:Carnauba)の葉の細孔および葉柄の分泌物から得られる植物性固体ロウです。用途としては、粒ガムや粒チョコレートなど食品のコーティングや化粧品・医薬品、カーワックス、プリンターのトナー、塗料、革の艶出しや磨き剤などの幅広い用途で使用されています。
カルナバワックスの組成
脂肪族エステル(約40 %)、4-ヒドロキシケイ皮酸のジエステル(約21%)、ω-ヒドロキシカルボン酸(約13%)、脂肪族アルコール(約12%)などから構成されている。ほとんどが直鎖長鎖エステルであり、安定性および酸化への耐性が非常に高く、総合的に酸化安定性は極めて高い(酸化しにくい)と考えられます。特徴は、ジエステルとメトキシケイ皮酸の含量の多さである。
硬化性
カルナウバロウは植物性ロウの中でも強靭性・硬さにおいて最も優れており、他の油性原料に少量添加することで硬度を上げる機能が非常に優れている
その硬さおよび強靭さから、脱毛時に使用されるブラジリアンワックスの基剤としても汎用されています。
耐温性
カルナウバロウは植物性ロウの中でも融点が72-86℃と最も高く、油性原料に少量添加し融点を上げることで、耐温性を向上させるため
動物性オイル
ミンクオイル
ミンクオイルは、動物のミンクの皮下脂肪から作られたオイル。
動物性の油分は革との相性がいいため、レザー用品の手入れに使用されているのです。
また、ミンクは女性の毛皮コートなどや襟巻きにも使用されており「毛皮の宝石」とも言われています。
元々はブーツの手入れを目的として、アメリカで作られたようですね。
ウエスタンブーツなどのアメリカ製ブーツが日本に輸入されたことで、ミンクオイルも一緒に日本に入ってきたということだそう。
今では色んなメーカーからミンクオイルが売られていて、有機溶剤などの添加物が入ったものや、ミンクオイルのみで作られたものもあります。
植物性オイル
シーダーウッドオイル
シダーウッドは、針葉樹を中心とする広い範囲の樹木を指す概念であるが、英語圏において類似の樹木にも cedar の名が付けられた結果、植物学的な分類が必ずしも一致していないのが現状で、シダーウッドと言っても様々な針葉樹が用いられている。そのため、用いられる樹木によって、そのオイル効果や河野は不定となってしまっている。例えば、シダーウッド・アトラス(Atlas Cedar)マツ科、シダーウッド・ヒマラヤ(Himalayan Cedar)マツ科、シダーウッド・バージニア(Eastern Red cedar)ヒノキ科、シダーウッド・テキサス(Cedar wood Texas)ヒノキ科などがあります。
シダーウッド・アトラスの組成
主成分がセスキテルペン炭化水素類でそれをさらに分類するとβ-ヒマカレン(約40~50%)、α-ヒマカレン(約10~20%)、γ-ヒマカレン(約10~15%)、α-セドレン(約5%)。
そしてそれに続くのがセスキテルペンアルコール類のセドロール(約5%)。ケトン類のアトラントン(約5%)となっています。
殺菌効果
シダーウッドの主成分の80%以上は、セスキテルペン炭化水素類で構成されています。セスキテルペン炭素類はテルペノイド(テンペル類)と言われ植物や昆虫、菌類、細菌などによって作り出される防衛物質やフェロモン等のセミオケミカル(情報化学物質)の役割があります。
テルペノイドは、微生物の活動を抑制する作用をもち、いわゆるフィトンチッドと言われます。
シダーウッドは、抗真菌作用がありカビの発生を抑えることができるといわれているんですが、それは、上記の作用から言われているものと思われます。
パームオイル
パームオイルとは、パーム(ヤシの木/palm)の油という意味で使われます。ヤシ油としては、ヤシ科植物ココヤシ(学名:Cocos nucifera 英名:coconut palm)の果実(ココナッツ)から得られる植物油脂のことを指します。しかし生産量的にはヤシ科植物ギニアアブラヤシ(学名:Elaeis guineensis 英名:African oil palm またはmacaw-fat)の果肉から得られるパームオイルほうが一般的に多く、これをヤシ油、パームオイルと呼ぶこともあり混同されることが多いです。
ココヤシの組成
ラウリン酸(約47%)、ミリスチン酸(約17%)が多くを占めており、また炭素数12以下(C12以下)の飽和脂肪酸を多く含んでいるのも特徴のひとつです。
ギニアアブラヤシの組成
パルミチン酸(約43%)、オレイン酸(約40%)が多くを占めており、残りはその他の様々な飽和脂肪酸を含んでいます。
ココヤシとギニアアブラヤシの違い
基本的なところでは、ココヤシ、ギニアアブラヤシどちらも石鹸としての利用が多く、それはそれぞれに含まれる飽和脂肪酸の界面活性作用や抗菌作用、洗浄作用を目的として使用されています。しかしそれぞれの組成の主な飽和脂肪酸に違いがあることからココヤシとギニアアブラヤシの効果に違いが現れます。まずココヤシに含まれる飽和脂肪酸のラウリン酸とミリスチン酸は飽和脂肪酸の中でも界面活性作用が強く、つまり界面活性作用が強いということは、オイルやクリーム、ローションを作る際に水溶性のものと脂溶性のものを乳化(混ぜ合わせる)ことができるという利点、革のケアにおいては革表面への浸透作用、洗浄作用や汚れを浮き上がらせる分散・凝集作用、革の中への保湿作用、革自体への柔軟作用、肌触りが良くなる平滑作用などがギニアアブラヤシと比較すると高いということになります。
それに引き換えギニアアブラヤシは、ココヤシと比べると飽和脂肪酸の洗浄作用は同じぐらいですが、主脂肪酸のパルミチン酸、オレイン酸は界面活性作用が多少低いためココヤシほどではない表面化活性作用なのではないかと考えられます。その代わりココヤシと比べるとココヤシの原産フィリピンやインドネシアですがあまり収穫できる量は多くなく、ギニアアブラヤシはインドネシアとマレーシアでギニアアブラヤシの方がパームオイルとして世界の8割のシェアを誇っており、つまりコスパとして、ギニアアブラヤシの方が安価に入手できるという利点がギニアアブラヤシの需要を増やこととなっています。
レザーケア商品には、基本的におパームオイルと記載されているのみで、ヤシの種類までは記載されていないため、ほとんどがギニアアブラヤシなのではないでしょうか。
追記予定
オゥリキュリー(Ouricury)ロウ、やしロウ、カンデリラロウ、甘蔗ロウ、綿ロウ、亜麻ロウ、オコチラロウ、ピサングロウ、及びエスパルトロウなど、随時追加していきます。

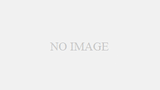
コメント