今回は、カメムシを寄せ付けないようにする植物についてのお話です。
カメムシについてですが、ここ近年になって特にカメムシの増加が注目されています。また、カメムシが多いと地震などの災害が起きるといった都市伝説もささやかれています。実際の話で例年全国的にもカメムシが増えているようで、農作物にも被害が出ており農林水産省からも「カメムシ注意報」が出ています。

▽愛媛▽神奈川▽鳥取▽山口▽和歌山▽高知▽徳島▽福岡▽香川▽京都▽兵庫▽熊本▽長崎▽大分▽愛知▽岡山▽千葉▽茨城▽埼玉▽栃木▽大阪▽奈良▽石川▽滋賀▽岐阜▽東京
カメムシが家に寄ってくる理由
カメムシは、紫外線の光を頼りに移動する習性があります。そのため、白という色は、紫外線を多く反射する性質があるため、虫が集まりやすくなります。
カメムシは、温かくて湿度の高い環境を好む傾向があります。白色は黒と違い光を吸収しないため熱くなりすぎず、虫にとって適温となりやすい環境にあります。
カメムシが好む植物としては、代表的なものでは枝豆や大豆などの豆類や、ニンジン、パセリ、コリアンダーなどのセリ科の植物です。しかし、種類によっては、アブラナにつく「菜のカメムシ」という意味合いでナガメというキャベツ、ノザワナ、ハクサイ、コマツナ、ブロッコリー、カリフラワー、大根、カブ、クレソンなどにも付く種類もあります。家庭菜園をされているご家庭にカメムシが出没する可能性が高くなります。
近くに川があればクレソンなどの外来植物が大繁殖している可能性もあります。近年では、日本全国の水辺で急速な拡散と繁殖を見せるオランダガラシ(商品名クレソン)が日本の在来種を駆逐し成長しており要注意外来植物に指定されています。
カメムシはスギやヒノキも好み、その場所で卵も産みます。
スギやヒノキ花粉が多いとその後に実をつける割合も多くなりますので、この実をカメムシが好んでエサとして食べるので成長しやすくなりました。近年では、公園にメタセコイアが増えたことにも由来するかもしれません。
メタセコイア:日本で化石が見つかっており、白亜紀(今から1億4500万年前~6600万年前)から日本に存在した樹木と言われています。1946年に中国四川省(現在の湖北省利川市)で現存していることが確認され、1949年、日本政府と皇室がそれぞれメタセコイアの挿し木と種子を譲り受け、全国各地の公園、並木道、校庭などに植えられました。

カメムシを寄せ付けない植物
※秋田県立横手高等学校の「クサギカメムシの忌避反応実験」でこの実験で用いたものの中でテンペル類が含まれるものに、忌避反応を示しめいている可能性が高いという結果が出ている。
ハッカ/薄荷がカメムシ忌避剤として含有され販売されている商品が多いが。横手高校の実験ではハッカ油に対してのカメムシの忌避効果は薄いようである。
スペアミント(スペアミント精油)
l-カルボン(80%)、リモネン(12%)
ペパーミント
ペパーミントに含まれるメントールは昆虫に対する強い忌避効果があり、さらにゴキブリやハエなどが忌避するハッカの含有量が非常に多いため虫除けとしての効果がある。
レモングラス(レモングラス精油)
シトラール(80%)
レモングラスには「シトラール」「シトロネラール」が含まれ、古くから蚊よけとして活用されている。
ユーカリ(ユーカリ油)
シネオール(74%)、α-ピネン(15%)
レモンユーカリ
レモンユーカリの葉の中には「p-menthane-3.8-diols」と呼ばれる成分が含まれており、蚊の成虫がこの物質を感知して逃げるため、レモンユーカリには代表的な忌避剤・ディートと同程度の虫除け効果が期待できるといわれています。
チョウジ/クローブ(チョウジ油)
β-カリオフィレン(12%)
クローブには強い殺菌・抗菌効果のある「オイゲノール」という成分が含まれており、刺激性もあるため昆虫や犬・猫、ネズミなどの生物には有毒となっている。 これがクローブが特にゴキブリに効果的と言われる。カメムシに対してどの程度かは不明。
ゼラニウム(ゼラニウム精油)
シトロネラール(24%)、リナロール(16%)
「テルピネオール」「シトロネラール」を含有し忌避効果があるとされている。
コウスイガヤ/香水茅(シトロネラグラス)
精油シトロネラオイルの原材料として知られ忌避剤として用いられる。牛も食べないほど美味しくない。





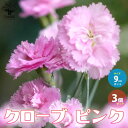


コメント