 ファッション
ファッション 海外有名人、俳優、女優の自転車ヘルメットの紹介
セレブやハリウッド俳優たちは自転車に乗るときに、どのようなヘルメットを着用しているのかまとめてみました。自転車のヘルメットの着こなしを真似るのも一つかもしれません。オシャレにヘルメットを選びましょう。
 ファッション
ファッション  食品
食品  食品
食品  便利グッズ
便利グッズ 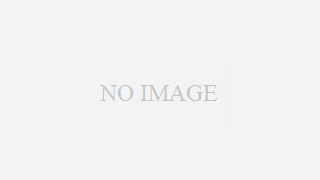 家具
家具 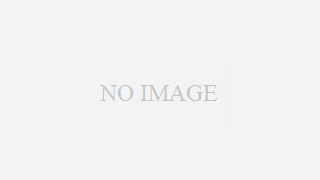 家具
家具 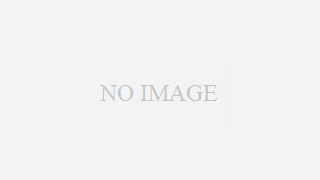 美容
美容 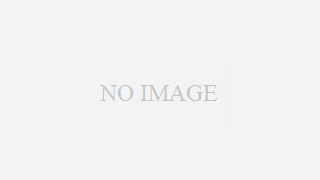 便利グッズ
便利グッズ 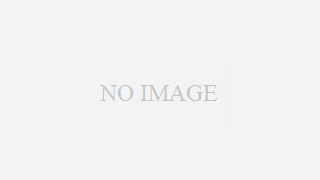 ファッション
ファッション  便利グッズ
便利グッズ